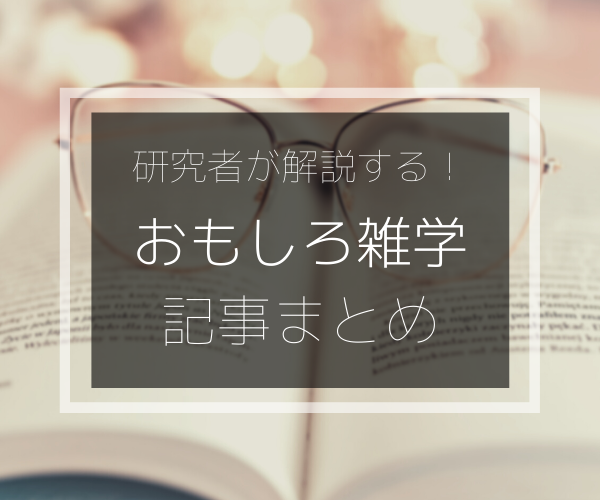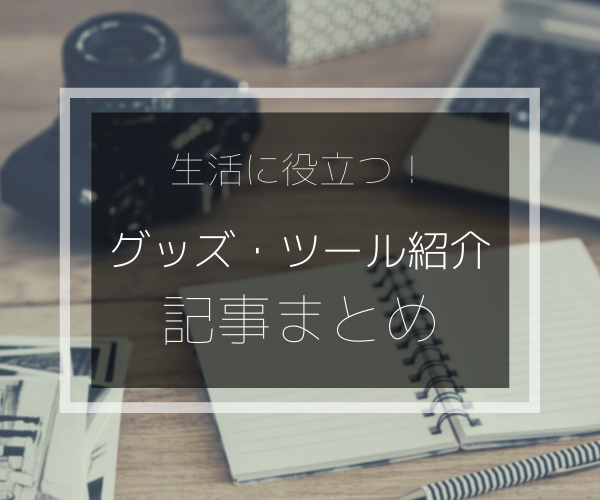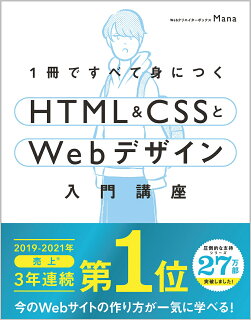【記事掲載】レバレジーズ株式会社様のレバテックフリーランスに当ブログ記事が掲載されました

ご無沙汰しております、モルモル(@morumorublog)です。
仕事・プライベートが忙しく、当ブログの運営をしばらく放置しておりました。
普段、全くと言っていいほど機能していないお問い合わせフォームなのですが、ある日レバレジーズ株式会社様から、当ブログの記事掲載依頼をいただきました。
このような依頼を受けた経験はありませんでしたが、放置気味の当ブログでも誰かの目に留まっていることを実感できて嬉しくなったので、即答で依頼を受け入れました。
レバテックフリーランスにて当ブログ記事が掲載されました
今回、掲載依頼のあった当ブログの記事は、以下の記事になります。
上記の記事が掲載されたレバテックフリーランス様の記事が以下になります。
今となってはすっかりお馴染みなテレワーク(在宅勤務)ですが、職場以外で仕事をするという性質上、仕事にメリハリをつけることが難しい、といった声も少なからずあるようです。
そこで、私が実践している「テレワークで上手く時間管理する3つの方法」を紹介した記事となります。
具体的には、以下の3つを実践することでメリハリのついたテレワークを実現できると私は考えています。
① 「タスク+休憩」をセットでスケジュールを決める
② 自分のスケジュールは関係者に共有する
③ 始業と終業時間をしっかり決める
要するに、職場となるべく近い状況を作り出すために、他者との情報共有や始業(終業)時間を徹底すること。
そして、自宅でどうしてもサボりたくなってしまうのであれば、思いきって休憩をこまめにとる(休憩込みでスケジューリングする)、といった工夫を取り入れることが重要と考えています。
記事の中では、図など用いてより詳しく解説しているので、ぜひご覧になって下さい!
レバテックフリーランスについて
今回、一通のメールで始まったご縁ということで、レバテックフリーランスについて簡単ですが紹介させていただきたいと思います。
※私自身が詳しくない業界・領域ですので、詳細な情報はぜひ会社様のホームページ等でご確認ください。
レバテックフリーランスとは?
レバテックフリーランス様は、フリーランスのITエンジニア向けの各種コンテンツを配信しています。
フリーランスITエンジニアの案件【レバテックフリーランス】≪公式≫
主には、ITエンジニア案件の取り扱い、フリーランスへの提案を行っているようで、【高単価】【継続提案】【案件数】といったところが強みのようです。
(私はIT業界に疎いですが、実際に紹介され散る案件の給与条件や、利用者平均年収を拝見して、想像を遥かに上回る好条件でびっくりしました。。)
案件の検索方法としては、スキル(Java、Phythonなど)、職種(インフラ、SEなど)、案件特徴(高単価、短期案件など)、勤務地など、いくつかのファクターから検索できるようです。
また、案件探しや税務サポートとして、エージェントを利用することもできるようで、サポート体制も整っているようです。
その他、無料のフリーランス相談会も実施しているようで、単なる案件仲介の業者ではなく、フリーランスをサポートする姿勢が見て取れるようなサービス内容に思います。
フリーエンジニアに向けたお役立ち記事が豊富
レバテックフリーランス様のサイトの中には、案件紹介に加えて、フリーランス向けのお役立ち情報が掲載された記事もあります。
フリーエンジニア向けお役立ちコンテンツ | レバテックフリーランス
これまでに大変多くの記事を執筆されているようで、ざっと数えたところ1000記事以上はありそうです。
私は専門外なので、細かい内容まではわからない記事が多いですが、「○○に必要なスキル」「未経験から○○になるためには」といった役に立ちそうな、読みたくなるような内容が多そうな印象でした。
ご掲載いただきありがとうございました!
今回、私の記事を掲載いただいたレバレジーズ様には大変感謝いたします。
このような経験は今回が初めてですが、私の記事が掲載された事自体ももちろん大変喜ばしいのですが、掲載いただいた会社様の情報を私自身も調べ、この記事にて発信させていただき、相補的に情報発信できたことが何より良い経験になったと感じています。
私は普段、研究者として専門領域の研究を業務を行っていますが、何も意識せず過ごしてしまうと、どうしても自分の領域にのみ目がいってしまい、視野が狭くなりがちです。
これを打破するためにも、自分の全く知らない領域に触れる機会というのはとても重要で、記事掲載という極めて小さいことでありながらも、ブログという媒体で、このようなコラボレーションを体験できたことはとても刺激的でした。
今後もこのような情報発信ができたらとても嬉しいです!
最後になりますが、このような機会をいただきましたレバレジーズ株式会社様には心より感謝申し上げます。
それでは!
オンライン学会に参加してみて感じたこと

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
新型コロナウイルスの影響で在宅で仕事をする期間が長く続いておりましたが、最近は出社する頻度も増えてきました。
一方で、他拠点の人とコンタクトをとる際は、出張が当面自粛のため、テレビ会議や電話会議を用いている現状です。
さらには、研究職という職種上、学会に参加する機会もとても多いのですが、コロナの影響で多くの学会が開催中止、あるいはオンライン開催となっています。
理由は、大人数が一挙に同じ会場に集まり感染リスクが高まることを防ぐためです。
首都圏ではなく、地方で開催されるような学会であっても、かなりの人数が参加するものについては、Webミーティングサービスを用いたオンライン開催となっています。
このような対応は過去に例がなく、運営側も参加者側も探り探りな感じがしました。
私自身も初めての「オンライン学会」に参加した感想をつらつらと記していきます。
※あくまでモルモルが参加した学会に限った話です。全ての学会について同じことが言えるとは限りません。
オンライン学会で良かったと感じた点
自宅(職場)から手軽に参加できる
学会は地方で開催されることも多く、そのために長時間かけて移動しなければならないことも多いです。
オンライン学会では、自宅や職場から参加することができるので、移動時間は完全にカットされます。
さらには交通費も完全カットのため、経費削減にもつながります。
通信環境さえ整っていれば、どこからでも学会を聴講できるので、便利な時代になったものだと痛感します。
講演の入退出が気楽にできる
学会の種類にもよりますが、規模の大きいものだと複数の講演が複数会場で同時進行するパターンも多いです。
その中から、自分の聞きたい講演をチョイスして聴講することになります。
学会会場は広いことも多いので、自分が聞きたい講演ごとに会場が変わる場合、移動が結構大変です。
また講演中に抜け出すこともしばしばあり、聴衆をかき分けて退出するのは少し気が引けてしまいます。
この点、オンライン学会では、「退出する」ボタンを押せば瞬時に退出でき、「参加する」ボタンを押せば瞬時に参加できるため、複数講演の横断的な聴講がとても簡単にできてしまいます。
私がいつも参加する学会は規模が大きいものが多いので、個人的にはこの点がオンライン学会の最大のメリットです。
スーツを着て大きな会場を時間に追われながら移動するのはなかなかしんどいものです。。オンラインなら優雅にコーヒーでも飲みながらのんびり聴講できます。
学会発表資料がWeb上にアーカイブされることがある
学会では、その分野の最新情報やホットな話題をたくさん聞くことができます。
得られる情報は価値の高いものばかりなのですが、それら全てを正確に理解して、後でフィードバックするにはそれなりの労力がかかります。
参加者の多くは、講演を聞きながらメモ帳に内容を記録したり、(本当はだめかもしれませんが)講演を録音したり撮影したりと、様々な方法で情報をキャッチしています。
これらの手段でも事足りる人もいるかもしれませんが、あとになって「ここの部分をもう一度聞きたい」「ここはなんて言ってったっけ」と講演を振り返りたくなるタイミングは少なからずあります。
通常の学会の場合は、聴講は「その場限り」であることが多いですが、オンライン学会の場合は、講演資料・映像がWeb上にアーカイブされ、一定期間内であればいつでも再聴講が可能になる場合があります。
あとで講演を見返せるので、学会で得た情報を後でより深く考察したいときにとても便利な機能で助かっています。
オンライン学会の良くなかったと感じた点
参加者とのコミュニケーションが非常に取りづらい
前述の通り、オンライン学会には多くのメリットを感じているのですが、それと同等にデメリットも感じます。
それが、学会参加者とのコミュニケーションがほとんどとれない点です。
現地に出向く場合は、多くの学会参加者と顔をあわせることになります。
もちろん、ほとんどの人が見ず知らず、あるいは顔見知り程度の関係ではありますが、同じ業界で働く人とのつながりは少なからずあります。
例えば、取引先、元同僚・先輩、会社横断的なプロジェクトの仲間など、社外のつながりはあるもので、学会というイベントは、このような人たちと同じタイミングで顔を合わせてコミュニケーションをとれる数少ない機会となります。
このつながりを維持するだけでなく、紹介という形でつながるが広がることも多々あるので、学会という空間は社外の人間関係にとってとても大事なものに感じます。
一方で、オンライン学会の場合は、基本的にはWeb上で講演を聴講することしかできず、参加者同士でコミュニケーションを取る手段はほとんどありません。
現地に出向いたときにはできていた、参加者同士でお互いの近況報告したり、誰かを紹介したり、雑談をしたりといった行為が全くできません。
本当に必要なことであれば、別に現地に出向かなくとも近況報告や紹介はできるのかもしれませんが、実際に顔を合わせてコミュニケーションをとれないのは、なんだか学会らしさがなく、味気ない感じがしてしまうのです。
「最新情報の入手」が学会参加の目的と考えると、講演を聴講さえできれば問題はないのかもしれませんが、大きな会場で知り合い同士でわちゃわちゃコミュニケーションを取るあの空間をしばらく体験できないとなると、やはり寂しさを感じてしまいます。
より便利で快適なオンライン学会に期待
今回は、コロナの影響で登場したオンライン学会に着目して、思うところを書いてみました。
総合すると、メリットの部分が大きいのかなとは思いますが、やはり上述したデメリットの面もなかなか無視し難い部分にも思います。
(あと、地方の場合は旅行気分も味わえたのですが、それが失われたのもとても残念です。)
オンラインツールは、共通したものが使用されることが多いですが、デメリットを解消するために、ツール側の改善が期待されるのかもしれません。
例えば、参加者が自由に作成できる雑談ルームを設けるとか、あたかも学会会場を模したような仮想空間を活用するとか。
現在の状況でオンラインで学会が開催できていること自体をまずは感謝しなければいけないのですが、今後ますます便利で快適なものとなるように、技術が発展することを祈っています。
それでは!
【ブログ熱が(少し)再燃】半年ぶりの記事更新

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
この記事を読んでくださる方に、私を認識している方がいるとは思えませんが、おひさしぶりです。
約半年ぶりの記事更新です。
ブログよりも熱中することが出てきたために、一時的に更新を止めていたのですが、再びブログ熱が再燃したため、再開しようかなと思った次第です。
一時期は、ブログは自分の人生で最高の趣味だ!とか言っていたと思うと、人の興味というものは本当にいい加減なものだと痛感します笑
ここで、これからは週○日更新を目標に!とか言ってしまうと足枷にしかならない(というか、どうせまた更新止める時期が来る)ので、書いたい時にゆるく記事更新していきます。
記事の内容は以前と特には変えず、仕事の話や論文紹介あたりをメインに雑記していきます。
当ブログのおすすめ記事を、トップページの上部にカテゴライズしているので、ご興味があればご覧いただければと思います。
久々にはてなブログを訪れてみて
約半年間、全くといっていいほどブログには手をつけておらず、かなり久々にはてなブログを訪れてみて、いくつか感じることがあります。
まず、私が読者登録していたブロガーさん達が、今も変わらず記事更新を続けていることに気づきます。
私がブログを離れている期間は定かではないですが、おそらく以前から引き続いて更新し続けていたものと思います。
自分が飽きっぽい性格というか、興味が移り変わりやすい性分のため、一つのことを長い期間打ち込むことができる人は尊敬しますし、そのような人が思ったよりもたくさんいることを痛感しました。
長く継続するためには楽しむことが一番だと思いますので、私も見習って無理ない範囲で楽しみながら更新していきたいと思います。
別の観点では、記事を全く更新していなくても、低空飛行ではありますがアクセス数が一定水準で維持されていたのが意外でした。
Google検索からの流入がほとんどで、私としては意外な記事へのアクセスが多くを占めていました。
この出来事についても感じることがあったので記事にしようかと思いますが、誰か1人にでも閲覧されているという事実は、ブログを運営するうえでやはり大きなモチベーションになります。
モルモルの中での当ブログの位置付け
これも以前と変わらず、ストレス発散がメインです。
自分の考えをアウトプットすることは、自分自身を俯瞰できたり、他人からの反応を得られたりといった多くのメリットがあり、結果的に活力が湧いてくる手段だと思います。
アウトプットの手段はいくつかあると思います。
例えば、SNSで短い文章を発信したり、人との会話で自分の意見を発信したりなど。
その中でもブログ、つまり、「記事を書く」という作業は、いくつかの行程があり、それなりの労力を必要とするアウトプット手段の一つだと思います。
もっと手軽なアウトプット手段はいくらでもありますが、この適度な労力、言い換えれば「面倒くささ」が、記事を完成させたときの達成感を増幅させ、ストレス発散につながっていると感じるのです。
というわけで、ブログ更新自体がストレスになってしまっては元も子もないので、ゆるーく継続していきます。
これからもよろしくおねがいします!
かなり短い文量ではありますが、久々に記事を書いてみるとやはり楽しいです!
同時に、頻繁に更新していた時期に会得していた作業ルーチン(記事レイアウトなど)を完全に忘れ去ったため、この程度の文量でも完成させるのに2時間近く要してしまいました。
これからは肩慣らししつつ、より効率的に記事を更新していきたいものです。
そんなわけで、これからもどうぞよろしくおねがいします!!
【2ヶ月で7kg減量】コロナ痩せが止まらない

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
テレワークの頻度が減り、出社する機会が大幅に増え、まだまだ不自由があるものの元の日常に戻りつつあります。
なかには、2ヶ月ぶりくらいに会うような職場の人もいて、「太った?」とか「髪切りました?」とか外見のことがよく話題になります。
実際、世間では「コロナ太り」という言葉が登場しています。
テレワークにより通勤がなくなったり、外出しないことで運動不足が加速し、太ってしまうことを指すようです。
(参照:30代女性の8割が外出自粛で体重が増えた!?「コロナ太り」「コロナ痩せ」の実態(Suits-woman.jp) - Yahoo!ニュース)
私も約2ヶ月ほど、ほとんど家から出ない生活が続くことがわかっていましたので、コロナ太りを避けるために、色々と注意をしてきました。
その結果、コロナ太りを防げたどころか、2ヶ月で7kgも体重が落ち、「コロナ痩せ」を達成してしまいました。
これまでの人生で、ここまで急激に痩せたのは初めてで、ちょっと心配になるレベルなのですが、体が明らかに引き締まり、夏に向けてちょうどよかったと思っています。
本記事では、コロナ痩せに至るまでに私が実践したことを紹介します。
食事制限
まず最初に注意したのは、食事の内容です。
家から出ない時点で、運動量は確実に減ってしまうので、摂取するエネルギーもその分減らさなければ太ってしまうと考えたからです。
炭水化物・脂質を減らし、タンパク質を増やす
まず、脂肪がついたり、太る原因になりやすい炭水化物、脂質の量を減らしました。
炭水化物に関しては、普段は朝、昼、夜全て白米を食べていましたが、朝だけに切り替えました。
昼と夜は白米の代わりに、絹ごし豆腐に切り替えました。
白米とは全然違う食感・味ですが、食べごたえはあり、今となっては全く違和感がなくなりました。
脂質に関しては、揚げ物を食べることをやめました。
それ以外は特に注意していませんが、明らかに脂質を多く含む食品(スイーツやファストフード)は避けるようにしていました。
一方で、タンパク質に関しては、全ての食事で増やすことを意識しました。
朝は、魚介類のタラをレンジでチンしたものを食べていました。
タラは高タンパク、低脂質、低カロリーとダイエットには最適な食材のようで、毎日食べていました。
(参照:タラ - カロリー計算/栄養成分 | カロリーSlism)
昼と夜は、鳥ササミをレンジでチンしたものをメインに食べていました。
ササミは高タンパクで有名な食材ですし、肉感がありとてもおいしいので全く飽きずに食べ続けられました。
これらに加えて、1日3食全てにおいて、カット野菜を一袋ずつレンチでチンして、青じそドレッシングをかけたものも食べていました。
(フライパンが面倒なので、基本レンジしか使いたくありません)
このように、太る原因になりやすい炭水化物・脂質を減らしつつ、満足感を得られるような食材をチョイスすることで、無理なく継続して食事制限することができました。
週に1食は好きなものを食べる
上記の食事制限も今となっては慣れてしまったものの、最初のころはどこか物足りない感覚が抜けませんでした。
そこで、「週に1食だけは自分がその時に食べたい好きなものを食べる」というルールを設けました。
私の場合、土日のどちらかの昼食をそれに当てていましたが、テイクアウトした牛丼やら、自炊して作ったカレーやら栄養成分は一切考えず、好きに食べていました。
そのときの幸福感は凄まじいもので、あらゆる脳内麻薬が分泌されているんじゃないかとすら思います。
ボディビルダーなどのアスリートの減量方法に1つに、「チートデイ」という似たような考え方もあるようです。
減量を進めると、体が飢餓状態と判断して恒常性(ホメオスタシス)を保とうとして、体重が減らなくなってしまう現象があるようです。
これを脱するために、好きなものを好きなだけ食べ、飢餓状態ではないと体を騙す日(=チートデイ)を定期的に設けることのようです。
(参照:こんなに食べても大丈夫!? 「チートデイ」がもたらす意外なダイエット効果とは | FORZA STYLE|ファッション&ライフスタイル[フォルツァスタイル])
私の場合はただのストレス発散ですが、こういった甘やかしデーは何事も必要なのかもしれませんね。
筋トレ+有酸素運動
今思うと食事制限だけでも十分だったように思いますが、コロナ太りを恐れるがあまり、筋トレと有酸素運動も取り入れていました。
筋トレは、随分前に買って使っていなかったダンベルを使って、主に上半身を鍛えていました。
左右それぞれ6kgのおもりをつけて、スクワットしながら両手のダンベルを天井に持ち上げるような動作を、腕が上がらなくなるまでやる⇒休憩のセットを30分ほど毎日続けていました。
有酸素運動は、以下の動画をYoutubeで見ながら取り組んでいました。
(簡単そうに見えますが、全部やると死ぬほどきついです。前半は特に、休憩が軽いランニングなので、休憩になっていない気がする)
また、脂肪燃焼のためには、「筋トレ⇒有酸素運動」の順番が良いそうで、上記の運動を毎日1時間くらいかけて取り組んでいました。
(参照:筋トレと有酸素運動はどっちが先?組み合わせ方は? | POWER PRODUCTION MAGAZINE(パワープロダクションマガジン))
鏡で自分の体を見て小さな変化に満足する
上記の取り組みを続けていると、少しずつ自分の体に変化が出てきていることに気づきます。
最初は、太るの避けることが目的でしたが、ちょっとお腹が凹んだ?とか、なんとなく顔がスッキリした気がする?といった小さな変化を目の当たりにすると、なんだか満足感が湧いてきて、もう少し絞ってみたい!と思えるようになりました。
その後からは、毎日自分の体を見るのが楽しくなり、食事制限も運動もただ辛いだけの作業ではなく、その先の成功報酬(体の変化)をイメージしながら、無理なく続けることができました。
何かを達成するうえでは、節目節目に達成感を感じることはとても重要なことなので、小さな変化であっても見逃さず、自己肯定してあげることは大切に思います。
まとめ 質素でストイックな生活でも幸福感は味わえる
以上、自粛期間でコロナ痩せを果たすまでに取り組んだことを紹介しました。
文字にしてみると、そりゃ痩せるに決まってるだろ!という感じですが、期待以上の太り抑制効果に自分でも驚いています。
このことを会社の人に話すとかなり驚かれ、なぜそこまでストイックに制限できるのか?と問われることもあります。
たしかに人によってはストイックに見えるのかもしれませんが、ただ苦しいだけではなく、「旨味」もあるから継続できているのだと思います。
例えば食事制限であれば、普段は食べたいものを好きに食べており、それはそれで幸せです。
一方、食事制限中は特にお腹が減って辛い時期もあります。
ただ、その空腹感のなかで食べる質素な食事は、本当に美味しく感じますし、普段以上に幸福感が味わえている気すらします。
空腹の質が違うというか、食事制限中は体が本能的にエネルギーを欲しているような気がしており、その分、口にする食べ物も一層美味しく感じているように思います。
このように、生活の質は下がったとしても、その中で幸福を感じることは十分でき、幸せは絶対値ではなく、相対値なのだなと痛感しています。
今現在もこの生活を続けており、コロナ痩せが止まりませんが、あまり痩せすぎると会社の健康診断でいらぬ心配をされそうで怖いので、ほどほどにするつもりです。
外出自粛で太ってしまい痩せたい方は、ほんの少しでも工夫や努力をこらしてみてはいかがでしょうか?
それでは!
「メンタルの強さ」には2種類のタイプがある

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
テレワークでの勤務体制が徐々に解除になり、会社に出社して仕事をする時間が増え、徐々にですが元の日常に近づきつつあります。
テレワークはメリットがある一方で、いくつか不満もあり、良い経験となりました。
特に、対面でのコミュニケーションがとれないことが大きな不満の1つでした。
最近は出社するタイミングも増え、この不満は解消されつつありますが、対面であるがゆえの不満点も改めて痛感しています。
それは、対面で高圧的な態度や強い言動をされると、よりストレスが溜まり、メンタルに影響するということです。
私の上司は、指示の内容は的確であるものの、どこか人を見下したような高圧的な態度をとることが多いです。
対面で話しをしていると、そこまで言わなくて良くないか?もっと言い方があるだろうと思えるような発言が多々あります。
同じ部署の部下の中には、この高圧的な言動に悩んでいる人がいる一方、何とも思っていないかのように平然としている人もいます。
これは人それぞれの「メンタルの強さ」が異なっているからだと感じます。
その人たちをよく観察していると、メンタルの強さには2種類のタイプがあると感じたので、紹介してみます。
そもそもメンタルの強さとは
そもそも「メンタルの強さ」とはどういう意味なのでしょうか?
以下の記事では、このように紹介されていました。
そもそも「メンタルが強い」って具体的にどういう意味?
メンタルが強い人とは、どんなことがあっても自分を保てる強い精神力を持つ人を指します。
トラブルが起きても慌てない、逆境でもくじけない、プレッシャーに強いなど、感情によって精神力が左右されることなく、いつでも同じパフォーマンスを安定して発揮できる人のことです。
さらに、逆境やプレッシャーすら糧にして、より高い成果を出せそうと奮起する人もいるでしょう。
要するに、何があってもくじけない精神力をもっているということだと思います。
予期する/しないトラブル、逆境に曝されても、慌てずに冷静に対処できるような精神状態を保てる人、ということかと思います。
トラブルや逆境を完全に避けることはできないことを踏まえると、メンタルの強さは、そのようなイベントが起きたときに、それらをどのように対処しているかという点に秘密がありそうです。
私の身の回りのメンタルが強い人も、トラブルや逆境に曝される機会が少ないのではなく、むしろ他の人よりもその機会が多いようにすら思います。
メンタルの強さには2種類ある
メンタルが強い人を観察していると、大まかに2つのタイプに分けられるように思います。
私の身の回りにいる人を例に紹介してみます。
ストレス要因を受け流すタイプ
1つ目は、「トラブルや逆境などのストレス要因を受け流すタイプ」です。
このタイプは、ストレス要因をそもそも自分の中に過度に取り込んでおらず、メンタルに影響するような状態にさせていないように思います。
私の職場のメンタルの強い人にインタビューしてみたところ、以下のような思考回路をしているそうです。
① 上司と課題Aについて話し合う
② 上司が高圧的な態度・発言をとる
③ 課題Aの解決という観点で、重要なのは上司の指示内容であり、上司の態度は一切関係がなく気にしても意味がない
④ 上司がどんな態度をとろうが、メンタルには影響しない
この人をよく観察すると、上司に高圧的な態度をとられた時、一瞬ムッとしたような表情をするのですが、その後すぐさまいつも通りの表情に戻るのがわかります。
まさにこの瞬間、高圧的な態度・発言というストレス要因を受け流しているのだと思います。
(ちなみにこの人は、会社で行われるストレスチェックのテストでいつも、「ストレスがほとんどない」という診断結果になるそうですが、受け流す工夫をしているだけでストレスがないわけではないと、診断結果にストレスを感じているようです。)
相手の態度や発言にムッとしたり、苛ついたりしてしまうタイミングは少なからずあります。
そこで、一歩引いてみて自分が向き合っている本質(上記の例で言えば課題A)に立ち返ってみると、相手の態度や発言などはどうでもよく、気にしても意味がないことに気づけるのかもしれませんね。
傷つくけど回復が早いタイプ
2つ目は、「ストレス要因に曝されて傷つくけど回復が早いタイプ」です。
このタイプは、ストレス要因を自分の中に取り込み傷つきますが、それを癒やすための工夫を取り入れることで回復することができていると思います。
私の職場の人にはこのタイプが多い気がしており、実際に話してみたところ、以下のような例がありました。
① 上司と課題Aについて話し合う
② 上司が高圧的な態度・発言をとる
③ その態度・発言に腹をたてる、後になっても引きずる、気にしてしまう
④ そのストレスを発散するために、仕事以外のことに打ち込む/仕事で上司を見返す
このタイプはストレス要因を受け入れてメンタルに少なからず影響がでてしまうため、メンタルを立て直すための何らかの工夫をしていると思います。
お気に入りの食べ物/飲み物を楽しんだり、趣味に没頭するなどはわかりやすい例に思います。
私の職場では、仕事で受けたストレスは仕事で挽回する、といった思考回路を持っている人も少なからずいます。
上司に理不尽な態度・発言を受けたならば、上司が一言足りとも文句を言えないような完璧な仕事ぶりで見返す、といったことを実践している人も見たことがあります。
たしかに、仕事で受けたストレスを仕事の中で挽回できると、満足感・高揚感はより高くなるような気がします。
このように、ストレスを受けメンタルに影響がでることを割けられない場合は、どうやって立ち直るかを自分なりに考えて実行することも重要と思います。
まとめ とにかく気にしすぎたら負け
私の職場で見る人の事例を踏まえて、メンタルの強さについて、「ストレス要因を受け流すタイプ」、「傷つくけど回復が早いタイプ」の2種類を紹介しました。
薬で例えると、前者が「ワクチンタイプ」、後者が「治療薬タイプ」とも言えるかもしれませんね。
病気(メンタルが傷つく)になる前にワクチン(受け流し術)を使える人もいれば、病気にはなってしまうけれども、自分なりの治療薬(ストレス発散術)を使える人もいるのだと思います。
強いメンタルを保つうえでは、より上流でストレス要因を防ぐという意味では、「ストレス要因を受け流すタイプ」がより好ましいのかもしれません。
一方、どうしても受け流せないこともあるので、その時にはしっかりストレス発散するような2段構えの考え方が重要なのかもしれませんね。
ストレス社会と言われる現代ですが、ストレス要因はできる限り受け流し、なるべく楽に生きたいものです。
それでは!
異様な職場風景を見て感じること

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です
緊急事態宣言が全国的に解除され、ほんの少しずつですが、元の日常に戻る兆しが見えてきた状況と思います。
私の職場も、全面的な在宅勤務が徐々に解除され、様子を見ながら出社人数を増やしていく方針となりました。
今週は約2週間ぶりに会社に出社しましたが、職場の風景が様変わりしており、驚きを隠せませんでした。
家に引きこもる毎日だったので、COVID-19の影響はメディアから間接的に知ることしかできませんでしたが、久々に出社して、その影響の大きさを実感しました。
まるで病室かのようなオフィス
普段、研究所に勤めていますが、実験するスペースとは別に、デスクワークするための個人スペースがあります。
デスクがいくつか隣り合うような島が複数ある、よくある配置なのですが、各デスクを完全に区切るような形で、巨大なビニール膜が張り巡らされていました。
一瞬、改修工事でもやっているのかと錯覚するほどの異様な光景でした。
あるいは、無菌室や病室を彷彿させるような見てくれでした。
近接のデスク同士の会話での飛沫防止を目的として急遽設置されたものとのことでしたが、感染防止策としてここまでの対応が必要になるという認識がなく、かなり衝撃的でした。
スーパーやコンビニでビニールカーテンが導入されていることは知っていましたが、これらは接する人数が段違いに多く、感染リスクが高いことを踏まえた策と認識していました。
スーパーやコンビニならまだしも、人の出入りもほとんどない1事業所がやることなのか?と思うところはほんの少しありますが、実際に効力があるかどうかが問題ではなく、万が一感染者が出てしまった時、万全の感染防止策はとっていたという事実があったかどうかが重要であり、そのために配置しているという背景もある気がします。
至るところにアルコール消毒液
研究所ということで、アルコールはもともと多く配置されていましたが、今では全てのドア、出入り口にアルコール消毒液のポンプが配置されています。
とにかく、素手を直接触れうる場所には全て配置されています。
実験室、会議室など部屋が連なった長い廊下があるのですが、部屋の前一つ一つに鎮座するアルコール消毒液が、入室を管理する門番のように見えてしまいます。
(なんとなく、ヘッドノズルが頭に見える)
実際、入室時はアルコール消毒が義務付けられているので、入室者は全員、この門番に管理されていると言っても過言ではない気がします。
不自然に配置される座席
ビニールカーテンとは別の対策として、4人がけのテーブルの対面の2席をはずし、片面の2席だけが配置された不自然なテーブルスペースも導入されました。
主に食事で使われるスペースですが、人が席につくと、全員が同じ方向を向きながら食事を取る異様な風景となります。
人の後頭部だけが見える、ジェットコースターなどのアトラクションに乗っている時の光景に近いです。
食事をするときも極力会話を控えている状況ですが、対面ではなく、横隣だとなんとなく会話がしづらく、幸いにも?会話が弾みません。
"人の目を見て喋れ" という言葉があり、これの本来の意図は知りませんが、正面に人がいて、しっかりと視認することは、円滑にコミュニケーションをとるうえで重要なことなのかもしれないと実感しています。
それでもいつしか慣れてしまうのが人間
このように、たった1ヶ月くらいの間に、私の職場風景は様変わりしてしまいました。
出社再開からまもなく、まだ "変な感じ" がするのですが、人間の適応能力は凄まじいものなので、いつの間にかこの風景にも慣れ、"普通"になってしまうのだと想像します。
そしていつしか、ビニールカーテンも取り除かれ、対面に人がいるようなこれまでの常識的な日常に戻った時、今度はその風景に "変な感じ" を覚えるのではないかとすら思います。
今回、新型コロナウイルスという予期せぬ外的要因によって、人々の生活様式に大きな影響がありました。
その変化に対して不満や違和感を覚えることは当然だと思いますが、一歩引いてみて、人間の適応能力の高さを考えてみると、少しだけ前向きに考えられるような気がしました。
職場環境が様変わりしたことに対して、不平不満を吐き出している人もいるようですが、これらは全て、職員の感染防止を目的としたやむを得ない策であり、協力姿勢を示す必要があることに思います。
不平不満をなんでもかんでも吐き出すのではなく、"仕方ないことだし、どうせいつか慣れるからまあいいか" と余裕をもつことも、時には大事かもしれませんね。
...とは言いつつも、ビニールカーテンだけは早く取り除かれて欲しいです。
マスク+ビニールカーテンの二重膜のせいで、すぐ近くの人と話すときでもそこそこ声を張る必要があり、結構大変なのです。
第二波の発生も抑止し、元の日常に近づいていくことを祈ります。
それでは!
【座ったままは時代遅れ?】スタンディングミーティングとは

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
各地域で緊急事態宣言の解除が進み、徐々にではありますがこれまでの日常に戻る兆しが見えてきたように思います。
私の職場も、1ヶ月弱ほど続いたテレワーク体制が徐々に緩和され、人数配分を調整しながら出社する体制に移ってきました。
もともと在宅勤務のシステムがほとんど普及していない会社でしたので、テレワークはとても新鮮であり、良い面も悪い面もあると感じました。
本記事では、テレワークでリモート会議(Zoomなど)に参加した際の経験を踏まえ、新しい会議のあり方「スタンディングミーティング」について紹介します。
リモート会議に体を動かしながら参加してみた
テレワーク中は、基本的にメール・電話ベースでのコミュケーションがメインでした。
加えて、会議に関しては、Zoomなどを用いてリモート会議を行っていました。
私の場合は、スマホから音声のみでアクセスしていたため、自宅デスクでパソコンとにらめっこしながら、声のみでやりとりする形でした。
この1ヶ月で計10回くらいはリモート会議をしましたが、最初の頃は律儀に椅子に座って、会社で行われる会議と同じように臨んでいました(音声のみという点になんとなく緊張していたのもあります)。
しかし、リモート会議に慣れてくる度に体勢がフリーダムになり、ついには椅子から立って、ゴルフの素振りをしながら資料をみつつ、議論に参加することさえありました。
真面目に会議に参加しろ!と言われたら何も言えないのですが、このとき妙に議論の理解が良くでき、発言もスムーズにできていた気がするのです。
もちろん会社でこんなことをやったら怒られるの間違いなしなのですが、「体を動かす ✕ 会議」の組み合わせが、思いのほか良い相乗効果を生んでいる気がしました。
そこで少し調べたところ、体を動かすまではいかなくとも、"立ったまま" 議論するスタンディングミーティングという考え方があることを知りました。
スタンディングミーティングという選択肢
スタンディングミーティングとは文字通り、「立ったまま行うミーティング」のことです。
主には以下のようなメリットがあるようです。
~ スタンディングミーティングのメリット ~
◉ 省スペースで、気軽に行える
◉ かしこまった雰囲気になりづらい
◉ 作業効率アップ
◉ 眠くならない、健康にもプラス
個人的に最も興味深いのは、「作業効率アップ」のメリットです。
情報ソースまで確認しきれていませんが、以下のようなエビデンスもあるようです。
米ワシントン大学で、同じ目的をもったグループを「椅子に座って作業する」チームと「立って作業する」チームとに分け、それぞれの心身に与える影響について調査を行いました。すると、立って作業したグループの方は心拍数が上昇したり、呼吸数が増えたりするなど、興奮状態が長く続くことが明らかになったのです。
私が素振りをしながらリモート会議に臨んだ時も、ひょっとしたら同じような現象が起きていたのかもしれませんね。
なんとなくのイメージでも、じっと動かずに考えるよりも、多少体を動かしているときのほうが頭が働きますし、作業効率アップしそうな気がします。
特に、新しいアイデアを出し合うブレインストーミングのような会議体の場合は、全員が定位置に座っているよりも、参加者が入り乱れてああでもない、こうでもないと議論したほうが、より多くのアイデアが生まれそうなことは想像できます。
このように、用いるシチュエーションは考える必要がありますが、これまでの常識であった "座ったまま"の会議に加えて、"立ったまま"の会議「スタンディングミーティング」はとても有用な考え方に思いました。
会議は座ったままと立ったまま、どちらがよい?
では、結局のところ会議は座ったままか、立ったままか、どちらのほうが良いのでしょうか。
スタンディングミーティングが向いている状況
前項でも少し触れましたが、会議の目的による部分が大きいのではないでしょうか。
前述したブレインストーミングのような、いわゆる「アイデア出し」が目的の会議の場合は、スタンディングミーティングは向いているように思います。
加えて、ボードに文字を書いたり、何かサンプル品を手に取りながら議論するような会議も、椅子に座るよりは立ったほうが効率が良さそうです。
さらには、そこまで込み入った議論の必要ない、短時間で終えれるとわかっている会議の場合も、ササッと集まれるスタンディングミーティングは適していそうです。
スタンディングミーティングが向かない状況
逆に、スタンディングミーティングが向かない場合はあるでしょうか。
参加者が大人数の場合は、まず向かないでしょう。あまりに人数が多い状況で起立してしまうと、無秩序に議論が進んでしまい、かえって効率が落ちそうです。
また、会議が長時間にわたる場合は、体力的観点から向いていない気もします。会議に参加するのは、必ずしも若い人や健康な人だけではないと思うので、そのあたりの配慮も必要な気がしますね。
以上、テレワークにおけるリモート会議の参加経験を発端とした、新しい会議のあり方「スタンディングミーティング」の紹介でした。
私自身もスタンディングミーティングの経験はなく、具体的なイメージはできていませんが、手軽にできる点やフランクな雰囲気が生まれそうな点でメリットが大きいように思います。
ただ、威力を発揮するシチュエーションには制限もありそうなので、どの会議にスタンディングミーティングを組み込むか、考える必要はありそうです。
「会議は座ったままと立ったまま、どちらが良い?」という議題を、座ったままグループと立ったままグループに分けて議論させて、どちらがより効率的に一定の結論を得たか、比較実験をやってみたいものです。
(どこかの会社でやってくれませんかね笑)
それでは!
【大学と企業の研究の違い】予想外の結果が出た時の感情

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
研究者というブログタイトルにしておきながら、研究者 っぽいことをほとんど記事にしていなかったので、最近感じることを踏まえて、「大学と企業における研究の違い」について、少し深堀りして紹介します。
以前、「大学と企業における研究の違い」について概略を紹介しましたので、ご興味があれば御覧ください。
本記事では少し観点を絞り、研究者においてよくあるシチュエーションである "予想外の結果(実験や考え方など)が出た時の感情" について、メーカー勤務中の今現在と、学生時代では異なる部分があると感じているので、紹介します。
(ニッチな話題ですが、同じように感じる方がいるのかどうか、非常に気になります。もし共感等ございましたらブックマークやコメントのほどよろしくお願いします!)
予想外な結果が出るシチュエーションとは?
業界にもよりますが、研究職においては実験業務を行うことが多々あります。
実験を行ううえでは、基本的に以下のサイクルで試行錯誤を繰り返します。
① 課題に対して仮説を立てる
② 仮説に対する解決策(実験)を考える
③ 実験を行い結果を得る
④ 結果を踏まえ、仮説を検証する(①に戻る)
仮説通りの結果が運良く得られれば、課題解決ストーリーの手かがりを得ることができ、一歩進むことができます。
一方で、仮説通りの結果が得られない場合もあります。むしろ、こちらのパターンの方が多いようにも思います。
「仮説と反する結果が得られる」と聞くと、一見ネガティブに聞こえるかもしれません。
実際、期待する結果が得られず残念でした、で終わるパターンもありますが、予想外の結果の見方を変えると、考えもしなかった新しい観点、手かがりを得られることが極稀にあります。
研究は未知の領域を切り開いていく作業なので、予想外の結果が得られることは全く不思議ではなく、上記のように知的欲求を駆り立てられるような新しい知見を得られる可能性があるため、これこそが研究の醍醐味であると思います。
このように、研究においては自分が立てた仮説に反する結果が得られるということは往々にして起きることであり、新たな知見を得るチャンスでもあります。
予想外な結果が出た時の感情
ここからは、予想外の結果が出た時の感情について、私の経験を踏まえて「大学」「企業」のそれぞれについて簡単に紹介します。
大学:知的好奇心が湧く、楽しい(ポジティブ感情)
私は大学時代、とある分野で約3年半くらい研究室生活を過ごしました。
与えられたテーマは非常にニッチな分野であり、蓄積された知見もほとんどなかったため、自分で仮説を立て実験する作業をひたすらに繰り返していました。
3年半かけて多くの実験データを得ましたが、研究課題に対する明確なストーリーを提示することができず、最終成果としてはかなりお粗末なものとなってしまいました。
理由としては、自分の仮説に反する予想外の結果ばかりでてしまい、考察の収拾がつかなかったことが挙げられます。
一方で、予想外の結果が得られたときは、
"マジか、なんで?!"
"もしかしたら面白い結果かもしれない"
"この結果を早く誰かと共有したい"
といったポジティブな感情をもつ機会が多かったことをはっきりと覚えています。
全体の成果としては粗末なものとなり反省点は多かったのですが、上記のような研究の楽しさを知る機会としては恵まれていたのではないかと今では思います。
結果的に、アカデミアの道ではなく民間企業に就職しましたが、研究という分野から離れなかったのはこの経験が大きかったと思います。
企業:不安感、嫌悪感(ネガティブ感情)
そんなこんなで企業においても研究職として、研究に関わることとなりました。
業務内容にもちろん実験はあり、基本的な進め方は「仮説⇒実行⇒考察」のサイクルで変わることはありません。
加えて、対行政、対民間、対学会など業界全体の基準作り、それに則った評価などレギュレーション関連の業務も生じます。
(参考:レギュラトリーサイエンスとは)
入社から時間も経ち、学生時代と同じように予想外の結果が得られることはあるのですが、その時の感情は打って変わってしまいました。
"なんでこんな結果でちゃうんだ"
"どう考察しようかとても悩むなぁ"
"もう勘弁してくれ"
学生時代は研究を純粋に楽しめていたように思うのですが、企業になった途端、予想外な結果が得られるとネガティブ感情が湧くようになってしまいました。
理由は明確に自覚しており、「スケジュール感の有無」に限ると思います。
学生時代は、特に外部と共同していたわけでもなく、基本的に自分のペースで研究を勧めていました。
大げさに言えば、卒業時にデータが有れば、進め方はなんでもありといった具合です。
一方で、企業においては、どの課題に対しても必ず「期日」が存在します。
単純な提出物だけでなく、"○月○日までに✕✕という知見を示唆するデータを取得すること"、といったように実験ありきの課題に対しても期限が生じます。
このような期限設定が積み上げられて、テーマ全体のスケジュールが構築されているわけです。
この期限付きの実験業務において、予想外な結果が得られたとき、知的好奇心よりも前に「スケジュールへの影響」がどうしても頭に浮かんでしまうのです。
これは企業という性質上仕方のないことではあると思いますが、スケジュールありきの研究というものに嫌気が差してしまうタイミングは正直あります。
私の部署は、いわゆる基礎・探索研究のような新しい知見を積極的に期待するような部署ではなく、レギュレーションに則り物質・製品を評価する部署であるため、予想外な結果の取り扱い方がそもそも異なるという点はあるのかもしれません。
それでも、研究は研究であり、本来の楽しさ・醍醐味である「知的好奇心」が後回しになってしまっている自分に、本当にこれで良いのだろうかと疑問を感じている次第です。
立場によらず知的好奇心は持ち続けるべき
企業という組織に身を置いている以上、企業利益を優先することがマストであり、それに付随するスケジュールに従うことはとても重要なことです。
そのうえでは、予想外な結果が得られた際にまず考えなければいけないことは、その結果をどのように処理すれば最小限のリソースで対処することができるか(スケジュールに乗せられるか)、だと思います。
それがたまたま、自分の知的好奇心と合致する方向性のものであれば良いのですが、なかなかそうはいきません。
だからといって、知的好奇心を失ってしまっては、研究者として本領を失ってしまう気がします。
ですので、"企業の" 研究者としての使命は果たしつつも、"本来の" 研究者としての知的好奇心は持ち続けるべきだと感じています。
第一歩としては、自分が面白いと感じた考えを、企業利益につながりそうな文言と上手いこと結びつけて、誰かに提案することに思います。
このような提案をこれまで全くしてこなかったわけではないですが、より多くの提案をすることで、「スケジュール重視」と「知的好奇心」の両側面を満たせる研究ができるのではないかと妄想しています。
以上、大学と企業の研究の違いの1つとして、予想外な結果が得られた時の感情を起点として、少し深堀りしてみました。
同じ研究であっても、色々な見え方があるものだと最近特に感じます。
そういう意味では、1つの部署に留まるのではなく、性質の異なる複数部署を経験したり、場合によってはアカデミアに戻るような経験を積めば、オンリーワンな人材になれるかもしれないなと思います。
現状にはいろいろ不満はありますが、学生では味わない経験ができているという意味では大満足なので、今後もほどほどに頑張ります。
ニッチな話題、かつ長々と自分語りで失礼しました!!
それでは!
人間の感情は本当にいい加減なものだと思う

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
しばらくブログを書くのをサボっておりました。
理由は、他に没頭することが見つかり、そちらを優先していたからです。
少し前までは、ブログが楽しくてしょうがなく、これ以上の趣味はないんじゃないかとさえ、思っていました。
しかし、他に興味があるものを見出した途端、熱が冷めてしまいました。
「熱しやすく冷めやすいタイプ」というフレーズはよく聞きますが、自分の今の状況も踏まえ、人間の感情は簡単に切り替わるし、本当にいい加減なものだと痛感しています。
きっかけがあれば感情はあっさりと切り替わる
私の今の現状がまさにこの通りで、一時期は時間を忘れて没頭していたブログであっても、他に興味のあることができた途端、ブログの優先順位は一気に下がってしまいました。
つまり、どんなに楽しく、自分が興味のあることであっても、たった1つのきっかけで簡単に感情(興味)が切り替わってしまったということだと思います。
振り返ってみると、これは必ずしも楽しいこと、興味のあることだけではない気がします。
仕事で重いミスをしたり、恋人に振られたり、ショックな出来事が起きて落ち込んでも、たった1つのきっかけで、あっさりと切り替わった経験が多いことに気付かされます。
このように、感情には楽しい、辛いと様々な種類がありますが、どんな感情であっても、たった1つのきっかけさえあれば切り替わる可能性があるように思います。
心理学的ホメオスタシスという考え方
話は変わりますが、「ホメオスタシス」という言葉はご存知でしょうか。
端的に言うと、「なるべく今の状態を維持しようとする働き」という意味だそうです。
基本的には、生理学、生物学において使われることが多いようです。
ホメオスタシス(homeostasis)は、「同一の状態」を意味するギリシア語が語源。生理学者W・B・キャノン(1871~1945)によって提唱されました。
ホメオスタシスは、外部の環境にかかわらず、一定の状態を保とうとする調節機能です。ホメオスタシスが働く具体例は、以下のとおり。
・気温にかかわらず、体温を36度程度に保つ。
・身体のなかに細菌などの異物がない状態を保つ。
・軽いけがをしたりかぜをひいたりしても、時間が経てば健康な状態に戻る。
・塩分濃度や血糖値など、体液の組成を一定に保つ。
・体内の水分量を一定に保つ。
・ダイエットを始めても、体重が減りづらくなる。(ホメオスタシスとは? 自分を “変える” メカニズムを解明! - STUDY HACKER|これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアより引用)
このように生体調節の概念として知られるホメオスタシスですが、心理学においても用いられるようです。
・心理学におけるホメオスタシスとは
心理学におけるホメオスタシスとは、「今のライフスタイルや環境をなるべく維持しよう」という心理です。心理的ホメオスタシスには、良い面と悪い面があります。良い面は、私たちの生活に安定をもたらしてくれること。心理的ホメオスタシスがなければ、A社に入ったと思えばすぐに飽きてB社に転職したくなるというような、落ち着きのない不安定な生き方になってしまいますよね。
悪い面は、自分を変えたいとき、新しい挑戦をしたいとき、心理的ホメオスタシスが足かせとなってしまうこと。せっかく始めたランニングが三日坊主に終わってしまうのも、勉強する習慣がなかなか身につかないのも、ホメオスタシスが従来の習慣を維持しようとするのが原因なのです。
(ホメオスタシスとは? 自分を “変える” メカニズムを解明! - STUDY HACKER|これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアより引用)
上記の文章をみると、心理、つまり「感情」についても、ホメオスタシスが働いているとも読み取れる気がします。
たしかに、楽しいことがあれば、いつまでもそれを続けたいし、そのサイクルを崩したくありません。
辛いことであれば、いつまでも自分を責めてしまったり、落ち込み続けてしまった経験があるので理解できます。
ですので、生体においては、肉体面・精神面のどちらにおいてもホメオスタシスが働いているということは、経験則的にも納得ができます。
しかし、上記の引用にも記載の通り、ホメオスタシスにもデメリットはあるため、脱却する必要性が生じることもあると思います。
例えば、辛い気持ちのとき、ホメオスタシスに従いいつまでも落ち込んだままでは、次の行動ができませんし、前を向けなくなってしまいます。
そのうえでは、感情のホメオスタシスからの脱却のポイントとなるのは、前項で述べた「きっかけ」なのではないかと思います。
感情のホメオスタシスを破る何かを探す姿勢が大事
生体においては、感情にもホメオスタシスが働いており、今の状況を維持したいという心理が働きうることを知りました。
現状維持とも言えますが、これにはメリットもある一方、新しいことに触れられなかったり、現状から抜け出さないといけないタイミングで抜け出せない、といったデメリットもあると思います。
これを解決するためには、自分が感情のホメオスタシスに曝されていることを認識して、そこから脱却するための「何か」を探す姿勢を持つことが重要に思います。
この「何か」は人によっても、状況によっても異なるので一概には言えませんが、とにかく今の自分の視野の外にあるものに目を向けることが大切なのではないでしょうか。
たった1つのきっかけで、楽しいことが移り変わっていけば経験の幅が出ますし、辛いことにも過度に落ち込まずに切り替えることができるのかもしれません。
感情なんてものはいい加減なもので、きっかけさえあればいくらでも切り替えることができてしまうという認識を持つことが大切に思います。
おまけ 「悩む」という行為は思考していない
最後におまけで。
辛い時や落ち込んんでいる時は、いつまでもくよくよしてしまうこともありますよね。
これも一種の感情のホメオスタシスなのではないかと思います。
普段Youtubeをよく見るのですが、本田翼さんの動画でこんな言葉がありました。
"人は、悩んでいるときは考えていない" (4:25くらい~)
悩んでいるときはあたかも必死に何かを考えて悩んでいるかのように思いがちですが、実は何も考えてないから、原因や解決策を考えたほうがいい、ということかと思います。
悩むというホメオスタシスから脱却するために、原因や解決策を考えてホメオスタシスから脱却する「何か」を見つけることが大事、とも解釈できる気がしました。
大好きな本田翼さんの動画でとても共感できるフレーズがあったので、ついでに紹介でした(最近ちょくちょく動画投稿してくれて嬉しい)。
というわけで、ブログの熱は少し冷めましたが、興味が完全に失せたわけではないので、今後も気まぐれに更新します。
今後ともよろしくお願いします!
固定観念にとらわれることのメリットを考える

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
"固定観念にとらわれるな"
様々な場面で使われるフレーズですよね。
私の職場でも、これと似たような言葉を良く耳にします。
◉ 固定観念にとらわれずに考えろ!
◉ 常識にとらわれるな!
◉ 固定観念に縛られるな!
新しいモノ・考え方を求められる研究所では、特に耳にするフレーズに思います。
確かに、新しい発想をするうえでは、固定観念や常識にとらわれない柔軟な思考が重要なのはいうまでもないのですが、なんだかあまりに耳にしすぎて、正直うんざりしてきたのです。
理由は2つで、そもそも固定観念って何?という疑問と、「固定観念にとらわれない=正しい」という、よくある考えを振りかざすこと自体が固定観念にとらわれているのでは?という疑念が生まれたためです。
固定観念にとらわれずにアクションすることは重要なのですが、あまりにその観点を意識しすぎると、不都合が生じることを実感しています。
そこで本記事では、「固定観念にとらわれないことが正しい」という固定観念にとらわれず、固定観念にとらわれることのメリットを考えてみます。
非常にややこしい。
固定観念とは?
固定観点の言葉の意味は以下のようです。
「固定観念」(こていかんねん)とは、「凝り固まった考え方や意識」を意味する言葉です。他人の言葉や周囲の状況によっても考えを曲げることのない、頑固な考え方や意識のことを指し、ネガティブな意味合いとして使うことが一般的です。
ある1つの考え方に凝り固まってしまう、他の意見を聞き入れる余地がない(頑固)といったところでしょうか。
一般的な認識もほぼ同じではないかと思います。
確かに、凝り固まった考えでいると柔軟な思考はできないので、新しいアイデアを生み出せなかったり、臨機応変さが失われたりとデメリットも多いと思います。
一方で、必ずしも悪い点だけでなく、メリットもあるのではないかと感じます。
固定観念の存在意義
この点について調べてみると、非常に共感できる記事がありました。
固定観念はきちんと意味があるから存在しているのです。
では、なぜ人間の進化の過程で固定観念が身についたのか
思考を節約するため
人間は「思考を節約するため」に固定観念を身に着けたのです。
私の職場では、最近は特に頻繁に、「固定観念にとらわれるな」というフレーズを耳にします。
それに呼応するように、仕事の中でたくさんのアクションが生じています。
"今まではそうだったけど、本当にそれで良いのか"
"実はもっと良い方法が隠されているのではないか"
こういった観点をもつこと自体は良いことだと思いますが、これらを実際に検討するためには「思考する労力」が必要なんですよね。
今までの考え方を覆すためには、従来の考え方の弱点、新たな考え方のメリットなど色々なことを思考する多大な労力が必要になります。
ですので、目の前の課題全てに対して、「固定観念にとらわれない」考え方をしてしまうと、労力が膨大になってしまいキャパシティーを超えてしまうのです。
実際、私の職場でも似たような現象が起きており、固定観念にとらわれないことを意識しすぎるがあまり、選択肢が増え続け、収拾がつかなくなっているような事例もあります。
このことから、固定観念にとらわれる(利用する)ことで、「思考する労力」を節約することも必要なのではないかと感じます。
固定観念にとらわれることのメリット
思考の労力を他のことに割ける
固定観念の存在意義である「思考の節約」という点を踏まえると、節約した労力を他のことに割けるメリットはあると思います。
人間は、何かを思考するときのキャパシティーには限界があるので、固定観念を用いて思考をスキップし他のことに割くことで、物事を効率的にこなすことができます。
決断が早くなる
固定観念にとらわれることで、思考をスキップできると考えると、物事を決断するスピードも早まると思います。
人には無意識に行っているような行動も様々ありますが、当たり前の行動はいちいち思考しないと考えると、これも固定観念にとらわれた結果なのかもしれないですね。
固定観念をどう扱えば良いのか?
このように、「固定観念にとらわれる」ことにはメリットもあるように思います。
一方で、「固定観念にとらわれない」ことにメリットがあるのも言うまでもありません。
では、結局のところ、固定観念をどのように扱うことがベストなのでしょうか。
個人的には、「課題の本質を考えて、本当に正しい選択なのかを見極めること」がまず最初に必要と感じます。
固定観念にもメリットがあるとはいえ、思考停止で実行してしまうようでは、他に存在するより良い選択肢を見落としてしまうかもしれません。
ですので、何かを考えたり実行する前に、懐疑的な目線で少し考えた後、それでも固定観念(=従来の考え)でも問題ないと判断できれば、固定観念にとらわれた行動のメリットが活かされてくるものと思います。
固定観念を使う時と、使わない時を上手く見極める力が前提として必要に感じます。
まとめ 固定観念にとらわれることは必ずしも悪いことではない
最近の職場の風潮になんとなく不満をもったことを発端に、「固定観念にとらわれること」のメリットを考えてみました。
凝り固まった従来の考えを持ち続けることは、生産性に制限ができてしまいデメリットが大きいので、固定観念にとらわれないことはたしかに重要です。
一方、なんでもかんでも固定観念にとらわれない視点に立ってしまうと、思考力のキャパシティーを超えてしまい、本末転倒になってしまうとも感じます。
固定観念と上手く付き合って、バランス良く利用することで、固定観念にとらわれることのメリットも発揮させることがベストなのかもしれませんね。
それでは!
【最高の癒やし】YouTubeの猫チャンネル おすすめ5選

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
外出自粛で自宅で過ごす時間が増えたかと思いますが、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。
自宅での過ごし方の1つに、YouTubeやAmazon primeなどの映像サービスを使う方は多いのではないでしょうか。
外に出れないとストレス発散も難しく、自宅で映画や動画を見れるのはかなりのリフレッシュになりますし、便利ですよね。
私は最近、YouTubeで「猫チャンネル」を見るのにドハマリしています。
もともと動物が好きで、特に猫は大好きなのですが、ペット禁止の物件に住んでいるので猫が飼えず、やむをえず動画で楽しんでいます。
猫好きも相まって、猫に関する雑学も以前に紹介したくらいです。
YouTubeを頻繁に利用するようになってからそれなりの時間が経ちましたが、私の登録チャンネル一覧は、いつのまにか猫チャンネルで埋め尽くされていました。
そこで今回は、私が特におすすめするYouTubeの猫チャンネルをピックアップして紹介します。
YouTubeのおすすめ猫チャンネル5選
私が普段良く視聴する猫チャンネルの中から、特におすすめのものを5つチョイスして紹介します。
見出し名がそのまま、チャンネル名です。
各チャンネルの特徴と、おすすめの動画を1つ紹介していきます!
短足マンチカンのプリン
◆特徴◆
・短足マンチカンのプリンちゃんの日常系動画
・短い手足、床に付きそうなほどのむっちりボディがたまらない
・最近はほぼ毎日投稿ペース
短足マンチカンのプリンちゃんと、飼い主のご夫婦との日常を映した動画をメインに投稿されています。
マンチカンにも種類があるようですが、プリンちゃんは短足の種で、てくてく歩く姿は本当に癒やされます..!
それでも意外と、走るのは俊敏なようです。
そんな "短足マンチカンのプリン" のおすすめ動画はこちら。
プリンちゃんが飼い主さんに爪切りされる動画なのですが、膝の上に乗っている格好が最高にかわいいです。
たぶん20回以上は視聴したと思います笑
猫って爪切りは嫌がるものなんですかね。動画を見ると、なかなか大変そうです。
スコスコぽこ太郎&うま次郎〜猫ちゃんねる〜
◆特徴◆
・スコティッシュフォールドのぽこ太郎・うま次郎親子の日常系動画
・顔つきが対照的で、どちらもかわいい
・最近は毎日投稿ペース(1日に2回もある)
スコティッシュフォールド親子のぽこ太郎(垂れ耳)とうま次郎(立ち耳)の日常を映した動画をメインに投稿されています。
飼い主さんとも仲が良さそうで、足元にまとわりつく2匹の姿には癒やされます。
そんな "スコスコぽこ太郎&うま次郎〜猫ちゃんねる〜"のおすすめ動画はこちら。
ぽこ太郎ちゃんがあくびした瞬間に、飼い主さんがすかさず、指をパクっとさせる動画です。
ちょっと前の動画ですが、最も再生されている動画のようですね。
パクっとした後にぽこ太郎ちゃんが飼い主さんの指を舐めてあげているのがたまらなく可愛いです..!
猫のレモンちゃんねる//Cat Lemon ch
◆特徴◆
・スコティッシュフォールドのレモンちゃんの日常系動画
・毛色が綺麗、まだ生後1年くらいなのにとても大きい
・最近はほぼ毎日投稿ペース
スコティッシュフォールドの長毛種のレモンちゃんの日常を映した動画をメインに投稿されています。
ぱっと見、スコティッシュフォールドには見えないくらい、とても大きな体つきをしている気がします。
そんな "猫のレモンちゃんねる//Cat Lemon ch"のおすすめ動画はこちら。
つい最近の動画ですが、冒頭でレモンちゃんの巨大さがよく分かる動画と思います。
長毛種なので、モフモフ感がたまりません..!
まだ1歳ということですが、これからまだまだ大きくなるんでしょうかね..?
MOCOxAMAN / もふ猫の暮らし-Cat life-
◆特徴◆
・ラグドールのモコ・アマン兄弟の日常、役に立つモノ、コトの紹介(Vlog)
・ラグドール特有のゴージャス感、動画編集がおしゃれ
・最近は週1回投稿ペース
ラグドール兄弟のモコ・アマンの日常と、猫生活で役に立ったモノを紹介するVlog形式の動画をメインに投稿されています。
ラグドールということもあり高級感が漂っており、どことなく落ちつきがある印象です(たまにケンカもしているみたいですが)。
また、オープニング、テロップなどの動画編集がとてもおしゃれで、ブログを運営する身としても憧れるレベルです。
そんな、"MOCOxAMAN / もふ猫の暮らし-Cat life-" のおすすめ動画はこちら。
"猫あるある" をモコとアマンが実践してくれているのですが、どれもめちゃくちゃかわいいです..!
猫用のメガネなんてものがあるんですね。
本記事で紹介する他の猫チャンネルよりも、登録者数や再生回数は少な目なのですが、動画1つ1つのクオリティが極めて高いように感じるので、今後伸びるのではないかと1視聴者として期待しております。
ひのき猫
◆特徴◆
・ミックス猫のひのきをはじめとした猫ちゃん達の日常系動画
・たくさんの猫ちゃんが出てくるので見ていて賑やか
・最近は毎日投稿ペース
ひのきちゃんをはじめとした計5匹の猫ちゃんたちの日常を映した動画をメインに投稿されています。
動画の中で複数の猫ちゃんが映ることもあるので、賑やかな感じで元気が出ますね。
そんな、"ひのき猫" のおすすめ動画はこちら。
この動画でチャンネルの存在を知ったのですが、子猫の豆大福が仰向けで寝転んでおり、飼い主さんたちにちょっかいされますが、全く動じずひたすらに寝続けます。
ここまで無反応だと心配になってしまうレベルですが、ぐっすり寝ていて本当にかわいいです..!
まとめ 全ての猫にありがとう
私が普段視聴する猫チャンネルの中から、特におすすめのものを5つ紹介しました。
これだけたくさんの猫動画がアップロードされていると、毎日猫ちゃんを目にすることができるので、もはや自分が飼っているかのような感覚になります。
(いずれは実際に飼ってみたいですが)
仕事で疲れた日も、かわいい猫の姿を見ると疲れも悩みもどこかに吹き飛ぶので、本当に感謝しかありません。
外出自粛で鬱憤がたまる時期ですが、猫ちゃんのかわいい姿に癒やされてみてはいかがでしょうか?
ここで紹介したチャンネル以外にも、たくさんの猫チャンネルがありますよ!
それでは!
朝活を継続するコツと体感したメリット【朝活の目的設定が大事】

おはようございます、モルモル(@morumorublog)です。
ここ最近、「朝活」というワードをよく目にします。
朝活とは、「朝の時間を利用して、普段できないことを実践すること」と定義付けされているようです。
ネットで調べてみると、朝活には多くのメリットがあるようで、著名人・偉人の多くは朝活を実践しているといった情報もたくさんでてきます。
朝活をやってみたい、あるいは実際にやってみてこのように感じたことはないでしょうか。
◉ 朝早く起きるのは、寝不足になりそうだし大変そう
◉ 朝早く起きたとしても、何をすればよいのかわからない
◉ 継続できる気がしない
私も以前から、朝活に興味があったため、少し前からチャレンジしています。
上記は私自身が実際に感じたことも含まれており、ネットで調べてもたくさん出てくる悩みのようです。
そこで本記事では、実際に朝活を実践している私の経験談を踏まえて、朝活を継続するコツと体感したメリットを紹介します。
私が朝活を始めた理由
私が朝活に興味をもった理由は、世の中の偉人たちが実践していることを知り、一種のあこがれを持ったことが最初のきっかけです。
Apple社のCEOのティム・クック氏は早起きであることが有名なようで、朝4時に起きて、Apple製品の顧客から毎日届く数百件のメールを全てチェックすることをルーティンとしているようです。
これをみて、"朝からこんなストイックに活動できるなんてすごい!"とシンプルに思い、影響されたことをきっかけに朝活を始めてみました。
私の場合、大体5時半くらいに起きて、本業の始業時間までの約2時間くらいを朝活に割いています。
朝活では主に、「ブログの記事を書く」か「本業のアイデア出し」の2つを実践しています。
朝活を始めてから大体2ヶ月くらいになりますが、今でも無理なく継続はできており、メリットも多く感じています。
朝活を継続するコツ
朝活にチャレンジする目的を決める
ネットで朝活について検索すると、"朝活で何をすれば良いかわからない" という悩みはよくみかけます。
早起きしてみたはいいものの、何もすることがなければあまり意味がないですし、継続もできません。
ですので、漠然と朝活を始めるのではなく、まずは朝活の目的をしっかりと考えるところからスタートすることが重要だと感じます。
私の場合は、「ブログの記事を書く」か「本業のアイデア出し」を軸に朝活をすることを決めましたが、これらはいずれも以下の理由から選定しました。
◉ 1人で集中して行いたい作業であるため
◉ 日中の時間には処理しきれない、時間を割けないため
◉ 自分が心から楽しいと思えるため
朝活は、静かな朝に1人で集中して作業できることが最大の特徴だと思います。
ティム・クック氏の膨大な量のメールチェックも、他の仕事が立て込んでくる日中よりは朝の方が捗りそうなことは想像がつきます。
朝活にやれることは様々ありますが、日中にはできないような、1人で集中して取り組みたいことを目的に設定することで、明確な目標ができ、継続意識が生まれてくるのではないでしょうか。
"毎日" 継続させる必要はない
朝活を継続するうえで、必ずしも "毎日" 実践する必要はないと思います。
前述した通り、朝活には目的設定が重要であり、その目的に応じて必要な時に朝活することが、無理なく継続するコツではないかと感じます。
私も朝活を継続してはいますが、必ずしも毎日ではなく、ブログや本業の状況や体調に応じて、臨機応変に朝活しています(毎日の時もあれば、週2, 3回の時もある)。
朝活あるあるの1つに、「朝早く起きることが目的になってしまう」ことがあるようです。
朝活の定義は、早起きしたうえで、普段やれないことを実践することですので、目的がすり替わってしまわぬよう、自分がやりたいことを選定することが重要に思います。
実際に朝活をやってみて感じたメリット
一日に使える時間の絶対量が増える
朝活を実践してみて、様々なメリットを感じています。
特に、一日に使える時間の絶対量が増えたことを最も実感しています。
朝に作業をこなしたとしても、時計を見てまだAM9時ごろであることを知ると、これから一日が始まるのに、もうここまで作業を終えている!と驚きます。
一方、朝早く起きている分、睡眠時間には気を使う必要があり、就寝時間は普段よりも少し早めています。
本当に気分が乗っているときは、睡眠時間を削ってもパフォーマンスが落ちることはないですが、基本的には就寝時間は早めたほうが良いと思います。
ルーティン作業よりもアイデアを考える作業が捗る
朝活では、あまり頭を使わないルーティン作業よりも、アイデアを出すような作業の方が捗るように感じます。
私が実践している「ブログの記事を書く」と「本業のアイデア出し」はいずれも、頭を使って独自の案を考える作業に近いです。
全くのゼロベースから取り組むというよりは、前日までにある程度の構想は練っておき、朝起きてから改めてアイデアを再考するようなイメージです。
朝起きて、頭がスッキリした状況でアイデア出しを行うと、突如として良い考えが浮かんだり、関連情報と結びつけたアイデアが浮かぶ機会が多い気がするのです。
睡眠と記憶定着の関係性として、レミニセンス効果という現象が知られているようで、睡眠を挟んだ朝の方が、過去にインプットした記憶が定着し、それに結びついたアイデアが生まれやすい状況になっているのかもしれませんね。
(参考:レミニセンス効果を理解して効率良い記憶法をマスター | MY FUTURE CAMPUS)
研究者という職業柄、新しい発想・アイデアを求められる機会が多々あるのですが、日常生活のなかでアイデアをふと思いつくような話はたまに聞きます。
なかには、仕事以外のプライベートであっても、常に研究のアイデアを探す思考回路で生活しているという超人も見たことがあります。
アイデアが浮かびやすい状況は人それぞれですが、朝活もその選択肢の1つかもしれませんね。
優越感・高揚感を得られる
朝活は早朝に行うものですが、基本的には多くの人が寝ている時間です。
そのなかで、自分がやりたいことを見つけて、早起きして活動している自分に酔うことで優越感・高揚感が得られます。
私も朝活をする時は、"朝活している自分かっこいい!偉い!"といつも自己満足に浸っています。
このような自己肯定感を得ることは、精神衛生的にも非常に良い影響があると感じ、意外と馬鹿にできないものと思います。
優越感を周囲にひけらかすのはあまり良くないと思いますが、ひっそりと自己肯定感を得たいときには朝活はとてもおすすめです。
まとめ 目的が明確な朝活は無理なく継続できメリットも多い
本記事では、私の体験を例に取り、朝活を継続するコツとメリットについて紹介しました。
結論としては、朝活は明確な目的を設定すれば無理なく継続できますし、たくさんのメリットが得られる素晴らしい活動だと感じます。
一方、やることを明確にしないと "ただの早起き"になってしまうリスクや、睡眠サイクルが変わることで体に負担がかかるといったデメリットもあります。
日中ではできない、朝活でしかできない自分が心からやりたいことをみつけ、無理のない範囲で朝活することが重要かもしれませんね。
ちなみにこの記事も朝活で書きました。
本日は休日ですが、既に一仕事終えた感覚でものすごく満足です!
本記事が、朝活に興味がある方にとって有用なものとなれば幸いです。
それでは!
テレワークでも上手く時間管理をする3つの方法【全て実践してみた】

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
昨今の状況で、テレワーク(在宅勤務)を実践している人も増えたかと思います。
かくいう私も、4月頭より基本的にはテレワークで仕事を進めています。
テレワークを自宅で行う上で、こんな経験はありませんか?
◉ 自宅だと集中できず、ついついダラダラしてしまう
◉ 他人の目がないため、ちょっとサボってしまう
◉ 仕事とプライベートのメリハリがつかない
つまり、テレワークになった途端、上手く時間管理ができなくなってしまうということです。
これらは全て、私自身が体験したものであり、周囲の知人にも似たような経験をした人が何人かいました。
テレワークには素晴らしいメリットも多いですが、上記のようなデメリットもあり、ぜひとも改善したいものですよね。
そこで本記事では、実際に私が実践している、テレワークでも上手く時間管理をする方法を紹介します。
「タスク+休憩」をセットでスケジュールを決める
テレワークの悩みの代表格として、仕事とプライベートの区別のメリハリがつけずらく、ついダラダラしてしまうことが挙げられるかと思います。
多くの場合は、自宅は仕事とは切り離された環境であるため、突然テレワークを行うことになると、仕事とプライベートの区別をつけられなくなってしまうのは、ある意味当然のことにも思います。
特に、テレワーク中の仕事に集中できず、不規則に休憩をとってしまったり、ついつい休憩時間を長くとってしまったりするようなことが多いのではないでしょうか。
これを改善するためには、一日のスケジュールの立て方を工夫することをおすすめします。
つまり、「タスク」でスケジュールを積み上げるのではなく、「タスク+休憩」のワンセットでスケジューリングすることで、規則的かつ決まった時間の休憩を挟むことができ、メリハリがつきやすくなります。
具体的には、以下のようなイメージです。

ざっくり言ってしまえば、休憩も仕事の一貫として取り入れてしまえばよいという考え方です。
自宅で仕事する分、本来やすらぐはずのプライベート空間に常に曝されることになるので、無理に仕事に打ち込もうとせず、いつもより休憩の回数を増やし、上手く仕事を溶け込ませるようなイメージです。
場合によっては、「休憩」のところには、家事などを入れ込んでもよいかもしれませんね。
時間を上手く区切り、有効活用することで、最大限のパフォーマンスを生むことができるのではないでしょうか。
自分のスケジュールは関係者に共有する
テレワークにおいては、仕事で関わる人との連絡手段はあるものの、直接会うことはありません。
つまり、「職場の人の目」がない状況で働くことになります。
人の目がないことは、無駄な緊張感がなくリラックスできるメリットがある反面、注意する人もいないため、ついついだらけてしまうデメリットもあります。
私もついつい、意味もなく休憩時間を長めにとってしまったり、スマホをちょくちょく見てしまったり、集中力に欠けた行動をとった経験があります。
これを改善するためには、「自分から人の目に曝されにいくこと」をおすすめします。
具体的には、自分の一日のスケジュールを職場の誰かに共有する方法です。
これにより、他人にスケジュールを伝えてしまった(宣言してしまった)事実と、これを達成できなかったら嘘をついたことになるといった背徳感から、大きな緊張感を得ることができます。
伝える相手は必ずしも、上司や先輩である必要はなく、仲の良い職場の人でも良いと思います。
実際私も、同僚と仕事の連絡をするついでにスケジュールを提示し合うことがありますが、相手に関わらず自分のスケジュールを誰かに伝えるだけでも、かなりの威力があることを実感しています。
それでもなお、仮にサボってもバレることは少ないと思うので、結局最後は気持ちの問題なのですが、自分自身を緊張状態に飛び込ませる工夫は、集中力を維持するうえでは重要な考え方だと思います。
業務開始と終了時間をしっかり決める
テレワークははっきりとした勤務時間が決められていない場合もあり、また自宅なのでいまいち仕事とプライベートのメリハリがつかないことも多いと思います。
前述したように、仕事とプライベートがある程度混合する(タスク+休憩)ことは問題ないと思いますが、いつまでもダラダラと仕事してしまうのも良くないです。
そこで、自分の中で、業務開始と終了時間を明確に決めると良いと思います。
テレワークにおいても定時が規定されているような職場であれば別ですが、必ずしも毎日定時が同じである必要はなく、フレキシブルに業務時間を前後にずらす工夫はできるのではないかと思います。
例えば、ある日は9時~18時、別の日は18時から用事があるため8時~17時に勤務といった具合です。
大事なのは、自宅だからといって、例えば夜遅くまでダラダラと仕事するのではなく、定時制のように業務開始と終了をしっかり決めることです。
そうすることで、スケジュールも立てやすくなりますし、プライベートとメリハリもつけやすくなるものと思います。
以上、実際に私が実践しているテレワークにおける時間管理の工夫の紹介でした。
プライベート空間で仕事することは違和感がありますし、慣れるのにも時間がかかると思います。
一ヶ月以上はテレワークで働いている私も未だに、最大のパフォーマンスは出せていない気がします。
新しい環境で働くことは新鮮味もあり楽しい部分もありますが、その分新たな課題も生じるので、自分なりの有用な改善策を見いだしていきたいところですね。
それでは!
2020年のゴールデンウィークを振り返る【思ったよりは充実した】

こんばんは、モルモル(@morumorublog)です。
一般的には本日5/6がGWの最終日、私は昨日までで、今日は半日分くらい仕事でした。
COVID-19の影響で外出自粛のGWでしたが、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。
私はGWに入る前にやることを決めていたものの、孤独感・閉塞感に押しつぶされるのではないかと想像していましたが、思ったよりは楽しめたGWでした。
日記感覚で少し振り返ります。
これまで以上にブログに注力できた
ほぼほぼブログづくしのGWでした。
アウトドアの趣味が多かったので、ブログをやっていなかったらと思うと、本当に戦慄します。
書こうと思っていた記事を書いたり、記事ネタのストックを増やしたり、いつも以上にブログに打ち込むことができてよかったです。
外出自粛の影響が大きいのだとは思いますが、アクセス数がいつもの倍くらいの水準が維持され、モチベーションにもなりました。
自分のブログに注力することに加えて、他の方のブログもたくさん拝見しました。
興味を持ったブログを無差別的に読者登録してしまいましたが、他の方のブログを読むのはおもしろいですし、とても参考になります。
最近は特に、食べ物系のカテゴリーのブログを見るのにハマってます。
ダルゴナコーヒーなるものが話題であることを知り、テレワーク中の飲み物として取り入れようと企んでおり、明日以降の仕事が楽しみです。
こんな具合で、インプット、アウトプットともに充実したブログ週間となりました。
インドアでも情報発信できるツールがあれば、気分が落ち込むことも減り、むしろ楽しみを見いだせるものだなと痛感します。
Webデザインに興味を持った
ブログに注力したことに付随して、Webデザインに興味がでてきました。
GW前半に、大幅にブログデザインを修正しましたが、そのなかでデザインに対するモチベーションが目覚めてしまいました。
当ブログで実践したカスタマイズは、私が独自に編集した部分はほとんどなく、基本的にHTML・CSSのコピペですが、自分で自由自在にデザインできたら面白いかもなと思った次第です。
もともと、細かい部分をカスタマイズすることに楽しみを見出す性分で、会社で使うプレゼン資料を作る時、内容よりも見た目に力を入れすぎて注意されたことがあるくらいです。
基本、何事も形から入るタイプで、実力は後から伴うものだと思っています。
ブログのカスタマイズにおいても、ほぼ同じ感覚が得られるので、時間を忘れて没頭できます。
経験のない全く新しい分野に興味を持つことができ、収穫の多い休暇でした。
とはいえ、このようなプログラミング?の知識は完全にゼロなので、これを機会にAmazonで評価が高めだった以下の入門書を買いました。
時間のあるときに勉強することを企んでいます。
デザイン、プログラミング系の知識を得たとして、できれば本業(メーカー研究職)にも活かせればと思いますが、まだそこまでの具体的イメージはありません。
趣味の一貫ではありますが、上手いこと相乗効果を期待して楽しみたいと思います。
初のオンライン飲み会に参加
このGWは "Stay Home" 極まっており、食料調達のために近所のスーパーに出向くくらいで、累計の外出時間はおそらく1時間にも満たなかったのではないかと思います。
どうせなら、GW前に買いだめし外出時間ゼロにでもしていれば、話のネタにもなってよかったと今更ながら後悔しています。
外に出ないことは感染拡大防止の観点ではベリーグッドなのですが、人と話す機会が激減することがデメリットです。
私もGW中盤くらいから無性に寂しくなってしまったため、数人の知人とLINEでオンライン飲み会をしてみました。
いずれ記事にするつもりですが、オンライン飲み会はメリットとデメリットがはっきりしていて、かなり新鮮でした。
知人いわく、会社の部署でオンライン飲み会が開催されることもあるようで、いつもなら "用事があるからキャンセルで" と言えるところが、このような状況で断る理由がなく困っているという話がなんとも悩ましかったです。
下手に体調が悪いとも言えないところがミソですよね。
せっかく便利なツールなのに、どこにでも不満点は生じるものなのだなと感じます。
プチ断食に挑戦した
"コロナ○○" というワードがいくつも誕生しているようですが、そのなかに"コロナ太り"があります。
家でやることがないと、食に走りたくなる気持ちは大いにわかります。私もこのGWはそれを危惧しており、注意はしていました。
しかし、何もせずにただ食欲を抑えるのは非常に困難、というか無理だと思ったので、以下を意識しました。
◉ 食欲以外に注力できることを見出す(=私の場合ブログだった)
◉ 食べないことによるメリットを理解する
何かを我慢するときは、その分を発散できる別の何かがないとやってられませんよね。
そこで、「食べないこと」、つまり「断食」をひらめき、そのメリットに関して少し調べてみました。
どうやら、断食による生体への影響に関する報告は多くあるようで、動物レベルでは断食により寿命が伸びた知見も得られているようです。
その他、血中のインスリンと似た役割をもつ「インスリン様成長因子1(IGF-1)」が老化の促進にも寄与していて、断食による血中グルコースの低下に伴い IGF-1 も減少することで老化が抑制されることを初めとした、いくつかのメリットが科学的に示唆されているようです。
(参考:断食をすると体の中で何が起こるのか?分子レベルで解明進む |お菓子と科学のメディアのOPENLAB Review)
というわけで、どうやら断食は体によさそうな知見もあるようなので、昨日5/5の夜から断食しています。お湯しか飲んでません。
今現在5/6の17時過ぎ、約22時間くらい断食しましたが、もう限界なので書き終えたらご飯を食べます。
断食の期間の相場がわかりませんが、とっさに「"プチ" 断食」と見出しを変えました。
正直ただただ空腹感と戦うだけな印象で、体への影響はよくわかりませんが、次はしっかりと方法を調べたうえで挑戦してみたいです。
以上、2020年のGWの振り返りでした。
緊急事態宣言の延長も決まり、まだしばらくはインドア生活せざるを得ませんが、自分が思っていたよりも適応できていて、少し安心しました。
とはいえ、まだまだ長期間戦であり、ひょっとしたら今のような生活様式が、これからの世の中のデフォルトになってしまうのではないかと思うくらいなので、今の生活スタイルをより充実させるためにいろいろ試行錯誤したいものです。
それでは!